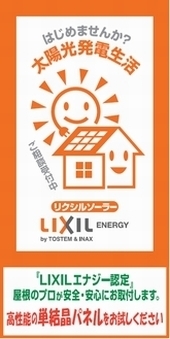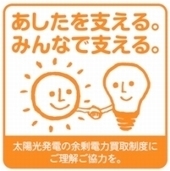良く自分たちの現場で耳にする用語で“雨仕舞い”という言葉があります。
単純に言うと『雨を片づける』という意味です。
けど、それがそんなに言うほど簡単ではありません。
シトシトと風情豊かに降る雨もあれば、
水しぶきを上げながら叩きつけるように降る雨もあります。
風に運ばれ横殴りに降る雨、時には風が舞う場所では
下から上に降る(吹き上がる?)時もあります。
簡単に片付かないのは、全くもって気まぐれな、生き物のような相手だからです。

この「雨仕舞い」とは別に、似たような意味で「防水」という用語もあります。
この方が聞いた方も多いかもしれません。
この“防水”を簡単に言うと「水の通らない材料を、特殊な工法で繋ぎ合せながら連続させて、水を漏らさない」ということになります。
これは、水を溜めておく状況で用いられる工法と考えていいかもしれません。
例えばプールとか平らな屋根なんかはよく防水工事をしているのを見かけます。
けど、工事して間もない時は良いですが、メンテナンスはわりと、こまめに必要です
繋ぎ目の工法の精度や、密着性、防水材料の耐用年数などに係わるところが大きく、長期間になればメンテナンスのスパンは短くなります。

これを踏まえて、もう一度「雨仕舞い」をちょっとだけ専門的に言うと、
「雨にぬれる場所、雨が降り注ぐ場所などに適した形、材質、配置の順番などによって、
その表面や隙間を流れる雨水を適切に処理し、雨もりの発生を防ぐ」ということになるかと思います。
次回に続く....